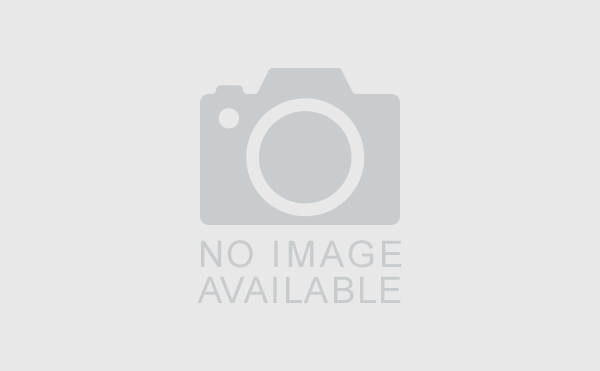「聴覚障害社会人&同僚のためのコミュニケーションワークショップ」を開催しました

筑波技術大学「聴覚障害者のためのキャリアサポートセンター」では、7月23日 水曜日に「聴覚障害社会人&同僚のためのコミュニケーションワークショップ」をオンライン(Zoom) 開催しました。
講師には、株式会社商工組合中央金庫DE&I推進部の笠原桂子(かさはらけいこ)氏をお招きし、聴覚障害者と聴者が職場でより良いコミュニケーション・働き方の改善ができるよう、コミュニケーションの留意点の解説およびグループワークを行いました。
<概要>
- 聴覚障害者と聴者との会議場面での聴覚障害者の情報取得状況の理解
- 職場で困りがちな場面の事例を検討し、改善策をグループワークで共有
当日は、参加者22名、見学者2名でした。いただいた感想を一部ご紹介します。
- 会議において音声認識を使用した場合、思っている以上に読むのが精一杯で、自分の考えをまとめたり意見することは難しいと感じました。また、ワークの中で、ろう者が活躍するためにはお互いが(ろう者と聴者)学び合う姿勢や、会社としての人材育成が大切であることを話されたときは大いに納得しました。
- 音声認識を見ながらメモ(聞きながらでもですが)は負荷がかかる。そのうえで、意見を短時間でまとめるのは大変な作業(慣れや経験も大きそう)。スピーカーが文字変換が正しくできているか確認しながら会議を進めることも大事。
- 聞こえにくい・聞こえない人の会議を体験して「こんなにつらいんだ」と実感したのが印象に残りました。
- 研修等では意識していましたが、会議でも資料を見せて・説明の流れがある方がよいこと。ただし、時間が限られた中での会議のため、そこを補う工夫をどうするか・(トランスクリプト誤字変換サポートなどもしているので、)トランスクリプトだけをみることになれていましたが、聞こえない中でのトランスクリプトがこれほどまでわかりにくいのかを体感できました。
- 会議で発言しないという聴覚障害の方が多かった。その理由は「内容を理解するのに精いっぱい」「会議の流れを止めてしまう」など。わからないことはないか聞かれても、聞こえているふりをしたり、「大丈夫です」と言ってしまったり。聴者の側がもっと想像力を働かせないといけないと感じた。
みなさまからの感想にある通り、聴覚障害者だけでなく、周りの聴者の方々にも一緒に情報保障の工夫を考えていただくことで、より働きやすい環境をつくっていけるのではないかと思います。本ワークショップでの気付きを、それぞれの職場の中で生かしていただければ幸いです。
※写真は講座当日の様子です。
※一部ぼかし処理を行っています。
今後も新たなイベントや講座の実施が決まりましたら、筑波技術大学のホームページや「聴覚障害者のためのキャリアサポートセンター」ホームページ等にてアナウンスいたします。